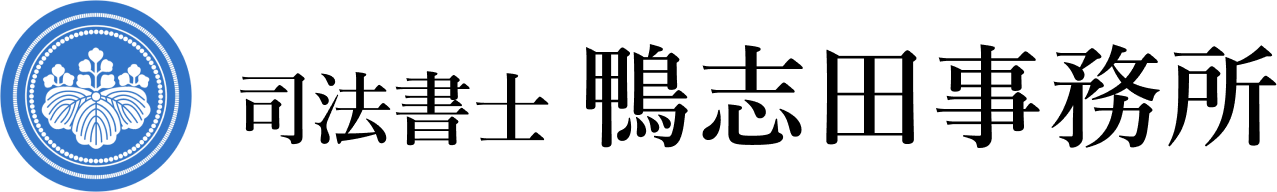Service
相続登記の手順や留意点など(ご自身で手続きをすることを検討されている方)
相続登記の流れについてご説明いたします。
第一段階:手続きが必要な不動産の把握
相続登記を要する不動産をすべて明らかにして手続きに漏れがないようにします。
<不動産の把握の方法>
A毎年役所から送られてくる固定資産税納税通知書を参照する。
※固定資産税納税通知書には非課税不動産の記載がない場合があるため、権利証、名寄帳もあわせて確認することをおすすめします。
B権利証の「不動産の表示」部分を確認する。
※すべての権利証を確認する必要があります。
C不動産所在地の区市区町村の役所で「名寄帳」を取得する。
☆名寄帳にはその区市町村に存在するすべての不動産が記載されておりその不動産評価額も記載されています。不動産の所在地区市町村が分かれば取得可能ですので、確実に不動産を把握するにはこの方法が適しています。
◎ワンポイントメモ
登記されていない建物については一般的には相続登記の対象にはなってきません。登記を行う場合には、まず表題登記という建物そのものの登記を起こさなければなりません。
第二段階:戸籍等の書類収集
相続登記に必要な書類には、一般的には、戸籍、住民票、遺産分割協議書、印鑑証明書、不動産評価証明書が必要になります。
①戸籍集め
●戸籍は亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの連続したすべての戸籍を用意する必要があります。この戸籍は本籍所在地でしか取得できないため、その区市町村の役所に直接出向くか、郵送で手続きする必要があります。
例えば、北海道の札幌市に本籍を置いてある両親のもとで生まれた方が東京都新宿区に本籍が移り、その後結婚して大阪市で戸籍を作り、神奈川県大和市に転籍して亡くなった場合を考えてみます。
ケース:札幌市→新宿区→大阪市→大和市
この場合に必要な戸籍とその取得する場所は以下のようになります。
①対象の方の親、祖父母の戸籍を遡り、生まれてから東京に転籍するまでの戸籍(札幌市市役所で発行)
②東京都新宿区に転籍してきてから結婚して大阪に戸籍を作って除籍されるまでの戸籍(新宿区区役所で発行)
③結婚して大阪市に戸籍を作って神奈川県大和市に転籍するまでの戸籍(大阪市市役所で発行)
④大阪市から転籍して、死亡除籍されるまでの戸籍(大和市)
◎ワンポイントメモ
・平成の戸籍法改正により戸籍がコンピュータ化されました。これにより同じ内容で区市町村で縦書き横書き2種類の戸籍がある場合が多々ありますので確認が必要です。
・集めた戸籍を法務局に提出することで「法定相続情報一覧図」を作成してもらうことができます。この一覧図は戸籍と同じ役割をしますので、登記申請時に戸籍の代わりに提出して手続きが可能です。
②遺産分割協議書の作成
遺言がない限り一般的には話合いで遺産の分割方法を決める場合がほとんどです。
不動産の引き継ぎ方を決めたら書類にして登記の際、法務局に提出します。
遺産分割協議書には必要事項を記載し、不動産を正確に記載する必要があります。
③その他の書類の取得
●相続人全員の戸籍については遡る必要はなく現在の戸籍で足ります。
●不動産を取得する方の住民票を取得します。
●相続人全員の印鑑証明書を用意します。
※有効期限はありませんが、被相続人が亡くなった後のものである必要があります。
●市町村役場、都税事務所等で発行される不動産評価証明書又は固定資産税納税通知書を用意します。
第三段階:登記申請書の作成及び書類の添付
書類がすべて揃ったら法務局に提出する申請書を作成します。申請書の書式は決まっていますので、ご自身で申請する場合には書籍等でお調べになるか、法務局の登記相談を利用して間違いなく作成する必要があります。
第四段階:登記申請書類の最終準備
戸籍等の書類及び登記申請書の作成が終わったら登記申請書と戸籍等の添付する書類、登録免許税を納税するための収入印紙貼付台紙をホチキスで綴じます。戸籍等の書類は法務局に申し出れば原本を返してもらえますが、返却を希望する書類をすべてコピーして「原本と相違がない」旨を記入して申請書に押印する印鑑で割印をする必要があります。
※戸籍については家系図のような相続関係を明らかにした図(相続関係説明図)を作成して提出すれば戸籍のコピーを提出しなくても戸籍の原本を返却してもらえます。
第五段階:法務局で登記申請
書類が整ったらいよいよ法務局に行き、書類を提出して登記の申請をします。印紙売り場で収入印紙を必要分購入し、提出書類内の貼付台紙に貼ります。不備がないことを確認したら窓口に提出します。登記がいつごろ出来上がるかは窓口横にあるボードに記載された「権利部補正日」をご覧ください。「補正日」を目安に登記が完了します。無事に完了した場合でも法務局からは連絡はありませんので、補正日以降に法務局に行き、書類を受け取る必要があります。なお、不備があった場合には法務局から登記申請書に記入した連絡先に連絡があります。軽微な不備であれば訂正することができますが、法務局に行って直す必要がありますのでご注意ください。
第六段階:登記完了
補正日まで特に不備の連絡がなければ登記が無事に終わったと思われますので、書類を受け取りに行きましょう。本人確認資料や印鑑など必要な持ち物がありますので事前に法務局に確認してください。
相続登記が完了すると登記識別情報通知という登記済権利証に当たる書類が発行されます。この書類は大変重要な書類ですので、なくさないように金庫等で保管することをおすすめします。ただし、法務局は他の返却書類と一緒にそのまま渡されますので、ファイル等を用意して保管しておくとよいでしょう。
また、返却書類には登記簿謄本は含まれていないので、別途窓口で取得する必要があります。相続した方の名前や住所等が間違えなく登記簿に記録されているか確認するために必ず取得しておきましょう。
(留意点など)
ご自分で手続きをする場合に特に難しい部分、いわば難所の部分は戸籍収集と、遺産分割協議書の作成と考えられます。ご自分で手続きされる方も、司法書士に依頼するか迷っている方も法務局での無料登記相談や司法書士の無料相談を利用して手続きの説明を受けることをおすすめいたします。一般的な説明戸籍の集め方やシンプルなものであれば遺産分割協議書の作成例なども示してもらえるようです。ただし、戸籍は人それぞれ異なるものであり枚数や取得する場所もまちまちです。そのため、特に本籍の変遷が分からない場合には亡くなった時点の戸籍からスタートして一つ前の戸籍を取得して、さらにもう一つ前と生まれた時の戸籍まで順番に取得していくことになります。遠方であればその役所まで出向くのはなかなか難しいでしょうから一般的には郵送で手続きをすることが多いです。戸籍に手書きで書いてある字(かなり読みずらいものも珍しくない)を読んでいくことになるので場合によってはその都度、法務局の相談を利用せざるを得ない場合もあるかもしれません。また、遺産分割協議書作成については、一般的な内容であれば雛形等を利用して作成することも可能です。ただし、不動産だけでなく、預貯金や不動産を売却してお金を分配するなど書き方が難しい場合もあります。
このように難所となるポイントが主に二つあり、司法書士に登記を依頼したり戸籍の収集を依頼するかどうかの基準はこの点で判断するのも一つの手です。
ポイント①
戸籍集めは本籍地が今まで何か所か動いていたり、郵送で取得する場合には役所のホームページから申請書をダウンロードし、小為替等と一緒に送るなどの手間や遠方の場合には時間がかかり、取得戸籍の問い合わせが役所からある場合があるので、かなりの負担がかかることがあります。
→今までの本籍地が把握できているか、手続きに必要な時間が確保できるか等によって自分で手続きする、一部を依頼する、すべてを依頼するを判断
ポイント②
集めた戸籍の確認や遺産分割協議書の作成、登記申請書の作成などの相談のために法務局に複数回行くことなります。法務局の相談は混雑しているため、1か月先になることもあるので注意が必要です。
→法務局までの距離や手続きをするための時間を確保できるか等によって自分で手続きする、一部を依頼する、すべてを依頼するを判断