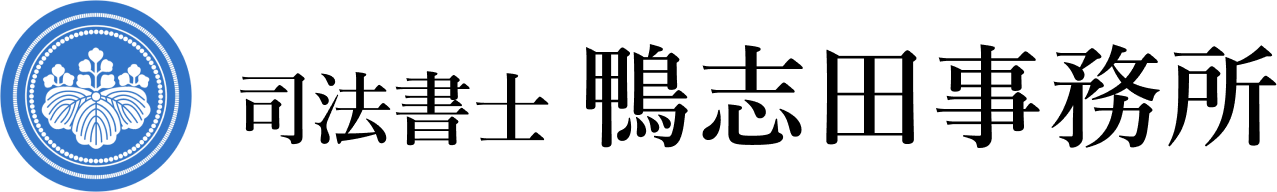Service
遺言に関するQ&A
遺言は自分の財産をもしもの時に備えて誰に引き継がせるかを示しておく書面のことです。遺言書を作成することで、紛争に発展する恐れのある相続人間での争いを未然に防ぐことが期待できます。また、作成する際に自分の財産を正確に把握するきっかけにもなります。その引き継ぎ方をあらかじめ決めておくことにより、安心することができますので、ご自身の相続財産についてご不安がある方につきましては作成をご検討いただくことをお勧めいたします。
Q1:作成した遺言はどうなる?
A
公正証書遺言→公証役場で適切に管理されます。
自筆証書遺言→原則、ご自身で保管する必要があります。家族等に預けたり、銀行の金庫に預けるなど確実で安全な方法で保管する必要があります。※法務局における保管制度を利用した場合、法務局で適切に保管されます。
Q2:公正証書遺言と自筆証書遺言の作成時に必要な実費の違いは?
A
【1】公正証書遺言→遺言の目的となる財産によって異なります。
「公証役場に支払う費用」と「証人(2名)に支払う費用」が主な費用の内容です。なお、司法書士等の専門家に相談した場合や書類の作成を依頼した場合はその費用が別途発生します。
(公証役場に支払う費用の例)※公証役場に支払う費用の詳細は公証役場にご確認ください。
例①:100万円以下⇒5,000円/例②:5,000万円を超え1億円以下⇒43,000円
証人への費用→依頼する証人の方にご確認ください。
弊所で証人をご依頼いただいた場合(二人の証人をご用意します)→¥33,000(税込)※交通費別
※公証人の方に自宅や病院に出張してもらう場合は上記費用の他に、公証人の方に出張費を支払う必要があります。
【2】自筆証書遺言→ご自身で作成し、自宅で保管する方法であれば0円、コストはかかりません。
※法務局による遺言保管制度を利用し、法務局での手続きを行う場合は法務局に遺言書1通につき,3,900円を支払う必要があります。
Q3:亡くなった後、自筆証書遺言に必要となる家庭裁判所での「検認」ってとは?
※公正証書遺言・法務局での保管制度を利用した場合これからご説明する検認は不要です。
A
→「検認」とは,亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にて、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。なお、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。検認を請求する際は家庭裁判所への費用の支払い(遺言1通につき800円)や検認申立書、戸籍などの必要戸籍の提出などが必要となります。
Q4:入院中や自宅療養中で遺言作成をする方が外出できない場合の作成方法は?
A
自筆証書遺言はどこで作成しても問題ありません。ただし、法務局での保管制度は、遺言書の保管の申請ができるのは,遺言者本人のみです。代理人による申請や郵送による申請はできず、手続きを行う日にご本人様が法務局に行く必要がありますので、外出が難しい場合はこの制度を利用できない可能性があります。
公正証書遺言の場合は、公証人の方が病院や自宅への出張を行っていることがほとんどですので、相談の上、出張をお願いして公正証書遺言の作成が可能です。※出張対応の有無は依頼をする公証役場にご確認ください。
Q5:作成時に必要な書類は?
A
自筆証書遺言→自分で作成し、自分で保管する場合は必要書類はありません。(作成時に認印で構いませんので印鑑が必要になります)※法務局保管制度を利用する場合は法務局が指定した提出書類(作成した遺言書、マイナンバーカードなど、住民票、申請書、保管手数料)
公正証書遺言→遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本、受遺者の住民票、手紙、ハガキその他住所の記載のあるもの、対象財産に不動産が含まれている場合には固定資産税納税通知書または固定資産税評価証明書と登記簿謄本、対象財産に預貯金がある場合は通帳(またはそのコピー)、証人の確認書類、遺言執行者の特定書類が必要となります。※詳細は利用する公証役場にご確認ください。